海外大進学という選択肢を当たり前にしたく、この連載に取り組んでいる藤原遥人です。前回の記事はこちらからご覧ください。僕は日本で生まれ育ち、海外大受験を意識していたものの結局日本の大学に進学しました。大学進学、憧れの米英大を一度自分の目で見てみたく、全て自分で計画して自費で米英に渡航し、在校生の知り合いの力も借りながら20校以上見学しに行きました。この連載では、そんな非帰国子女純ジャパの僕から見た海外トップ大の実態を書いていきます。今回はアメリカ東海岸後編と、番外編のミネルバ大学です。
・Chicago University
・Minerva University
Yale University

元々行く予定はなかったのですが、Google Mapを見たら、ニューヨークから電車で2時間の距離のコネチカット州にイェール大学があったので、夕方から数時間だけ、見るだけ見てみようと、弾丸で行ってみました。
授業に忍び込むことは無かったので、幾つか大学の建物を見ただけなのですが、その地域の空気感や建造物の外装内装が、今回行った大学の中で一番好きでした。8つの優秀私立大学群Ivy League(アイビーリーグ)の内上位の大学の一つであるイェール大学、Ivy Leagueらしい荘厳でイギリス的な趣のある由緒正しき大学という感じでした。特に食堂の大きさ、5階建て分はありそうな天井の高さは、ここで毎日食事をして学友と会話をする学生生活は有意義だろうなと、素直に憧れました。大学の空気感なら、イェール大学が一番行きたいなという感じでした。旅を始める前は、高校時代からの憧れと世界一の大学という名声から、ハーバード大学が一番行きたいと思うのだろうなと予想していたので、行こうとも思っていなかったイェール大学に対してその感情を抱くのは意外でした。是非一度訪れてほしいです。

Chicago University

親戚がシカゴに住んでいたので、2週間の東西横断旅が終わってから行ってみました。東大の友達の、シカゴ大学に進学した高校時代の友達を紹介してもらい、案内してもらいました。シカゴ大学は経済学が有名で、「シカゴ学派」という派閥があるほど独自に成長しています。経済といえばシカゴ、シカゴといえば経済といった感じで。そのためシカゴ大学の1/4は経済学で卒業するそうで、MITにとってのCopmuter Science (プログラミング的な専攻)がシカゴ大学にとっての経済学だそうです。実際に授業を一緒に受けさせて貰った時は、教授が黒板に計算式やグラフを書いて、囲うように並んだ100人ほどの学生がそれについて行く、古典的な授業が展開されていました。良い伝統の受け継ぎ方を体現している気がして好きでした。
キャンパスの雰囲気も、建物に蔦が絡んでジブリ味を帯びた建物があったり、伸び伸びとしたキャンパスの雰囲気がとにかく好きでした。競争というより自分のペースで学ぶ雰囲気がありました。シカゴ大学は3年次から編入で入る人が割と多いらしいのも特異的でした。

米大学受験を経験した友達に、州立大学と私立大学の違いを聞いてみたところ、州立大学はその州出身者が多いため多様性が少なく、また人数が多いため専攻を決めても人数制限が発生して受かるかどうか分からない、加えて教室の大きさに制限もあるため履修できる授業の選択肢も減ってしまう可能性があるのが大変だそうです。日本で言うところの地方国立大のようなイメージだと話していました。確かに公立大学の機能として地域の学力の底上げがあるでしょうから、そうなるのも当然だと思いました。実際にカリフォルニア州立大学であるUC BerkeleyやUCLAを見てそのような肌感は納得できました。
一方で私立大学は、アメリカ中から、そして世界中から学生が集まるため多様性があり、ほとんどの学生が寮に引っ越してきて一斉に学生生活をスタートするため状況が一緒で一体感やコミュニティ意識がある。人数も州立大学ほど多すぎないからディスカッションベースの授業も多く、ただ聴くだけの授業に収まりづらいと話していました。また、州立大学なら地域差による大学の「色」が出やすいからどの州立大学に行くのかは違いが生まれる一方、私立大学はある程度以上のレベルの大学ならどこもさほど違いがないのではないかと話していました。確かにハーバード大学やブラウン大学の全寮制やあらゆる伝統は、大学への帰属意識と横の繋がりを強固にしていると感じましたし、正直大学めぐりの後半からどの大学に行っても同じなんじゃないかと思ってしまうほど、カリキュラムの内容や学生生活の雰囲気に違いは感じなかったことも踏まえると納得できる内容でした。
話は変わって、アメリカの大学の宿題量が日本の大学のそれに比べて圧倒的に多いと聞いたことはありませんか。実際、アメリカの大学生は月から金まで毎授業100ページものリーディングを出されて次の授業までに読んでこないと、それを前提に進められる授業についていけないとそうで、毎日深夜まで宿題に追われて図書館で寝る生徒も多いそうです。日本の大学に通う僕としては、なぜそこまで宿題量に差が出るのか気になっていたのですが、実際に現地校に通う友達の様子を見ると、どうやらアメリカの大学では原文を読んで学習する一方、日本の大学では参考書を読んで学習するから分量が違うのではないかと考えました。僕の狭い経験からの印象と、文系学問の一部に限った話かもしれないのですが、例えば東大で哲学の授業を受けたら、こういうことを言った哲学者Aがいて、またこんなことを言った哲学者Bがいて、100年後には哲学者Cが現れて、と意義や歴史的役割から、全体を抽象的に概観するような、いろんな主張をある軸でまとめる「参考書」的な学び方をする傾向があります。原文を読む授業が稀であることの証拠に、「〇〇の〜〜論を読む」と言う授業が幾つかあります。一方、アメリカでは実際に哲学者Aの出した原文を読んでみて読解して考察してみるといった、より狭く深くの学び方をするため、具体的に字面を読んでいく必要がある。だからその分時間がかかるし宿題が多いのではないかと思います。僕は本を読むのが苦手なので好きな本と必要な本しか読みたくなくて、日本の勉強の仕方のほうが合ってると思います。ずっと日本で勉強してきたからその勉強の仕方をする頭に仕立て上げられてしまっただけかもしれませんが。
Minerva University (番外編)

番外編として一風変わった最近できた大人気大学を紹介したいと思います。ミネルバ大学はアメリカを拠点として在学4年間のうちに世界7カ国に滞在するオンラインの大学です。各学年100人ほどの少人数制で、全員で同じ寮に住みます。サンフランシスコから始まり、半年ごとにインドやアルゼンチンや台湾など世界中にある寮に移動していきます。キャンパスはなく、ミネルバ大学が独自に作ったZoomのような授業システムを使って、毎日オンラインで授業を受けます。オンラインなのでキャンパスはなく、みんなで同じ寮に泊まって、それぞれのパソコンで部屋やカフェから授業を受けます。上の写真は寮のリビングです。
授業内容は普通の大学と同じでComputer ScienceやEconomics、Statisticsなど理系科目をより打ち出しているのですが、勉強方法が一線を画していて、より効率的な勉強方法を研究した人が作り上げた最強のカリキュラムに則って勉強するそうです。
実は高校生の時にミネルバ大学の高校生プログラムに半年間参加しており、All Englishの授業やディスカッションに初めて参加したのがこのカリキュラムでした。予習で読まなくてはならないリーディングの記事が送られてきて授業準備をし、授業中はホワイトボードや理解度を示す絵文字を使ってオンラインでも理解度が損なわれないようにし、授業後は確認テストと短い感想を書いて終了、という流れでした。すごく面白かったですし、確かに学んだ内容は3年半経った今でもある程度覚えています。

ハーバード大学と東大の交換留学として1週間ボストンに行く際、トランジットでサンフランシスコを通ったので、当時の高校生用プログラムに参加してから実際にミネルバ大学に入学した友達を訪ねて寮に入れてもらいました。日本人は他にも3人いて、生徒は世界中から来ていました。カザフスタン人やモンゴル人など初めて会う人種の人とも話せたし、逆にアメリカ人はほとんどいなかった気がします。寮は普通の大学と同じルームメイトと2人部屋で、共通リビングでみんなご飯を作ったり話したりしていて、少人数であることもあって仲良しでした。
中には東大に入ったもののより自分に合った環境を求めてミネルバ大学に入り直した1つ上の先輩もいたり、数代前のミネルバ大生にも東大を辞めてミネルバ大学に入り、寮があるアルゼンチンのブエノスアイレスでサッカーチームに所属しながら学生をしている人もいます。
この大学の面白いところは、ある程度教えられずとも独学で勉強ができるような優秀な学生を本当に世界中から集めて、同じ環境で化学反応を起こさせる&場所を半年おきに変えることで現地でのインターンシップに取り組めたり自分のやりたいことに大学の枠に収まらずに打ち込めるところだと思います。
入試方式も面白く、合格した友達に聞いたのは、普通のアメリカの大学は事前に書いて提出したエッセイを元に合否を決めるのに対し、ミネルバはオンラインテストで時間制限を設け、その場で書かせた短いエッセイや2分間の自分の思いやバックグラウンドを喋るテストなど、その場でやらせて嘘偽りのない人物を取るという採用方法を取っているそうです。確かにアメリカの大学入試がエッセイという点数化しづらい方式を採用しているせいで、お金持ちの中国人がエッセイ会社に高いお金を払って合格できるエッセイを書いてもらうという事案も存在しているそうですし、その場でやらせるというのは面白いなと思いました。
学費も、固定費が少ない分普通のアメリカの大学の半分ほどでした。大人気の大学で、倍率がハーバード大以上と謳っているようなのですが、友達曰く入試難易度はそれほど高くなさそうです。というのもできたばかりの大学で多様性を重んじている&卒業生の進路でブランディング化したいので、例えば日本で最難関高校に所属している程度の学生でしたら、履歴書でだいぶ有利に立てるそうです。東大から海外大に1から入り直す例はほとんど聞かないのですが、2人もその先例がいることは、東大に入学したことがミネルバ大学から見てかなりよく見られていることの表れだと思います。
7カ国に住む経験をしながら英語で学べる環境はかなり魅力的なのと、現実的に入学できそうだったので僕も再入学するか真剣に考えた程でした。教育業界としても新しい試みをしている機関なので、ミネルバ大学の動向は要チェックです!
著者紹介
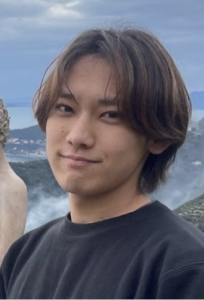
藤原 遥人(ふじわら はると)
開成高校在学時代、学校で教えないことを高校生が中学生に教え、勉強の面白さを伝える塾、寺子屋ISHIZUEを創業。現在東京大学文科一類を休学中。東大では、ハーバード大学とアジアのトップ大学の国際交流を図る学生団体HCAPに所属。休学中はアメリカ横断やヨーロッパ一周一人旅など海外への視野も広げている。

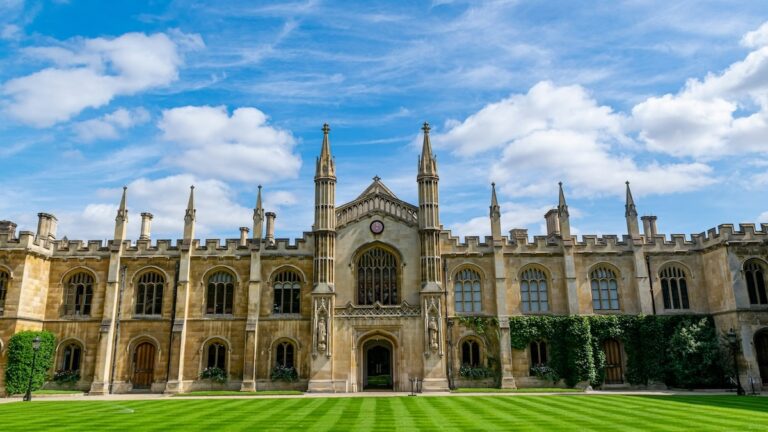
![藤原遥人の海外大放浪紀[第6回]米大学見聞録(東海岸中編) -Brown University, Columbia University, New York University-](https://studypass.jp/wp-content/uploads/2025/03/kaigaidai_main-375x211.jpg)
