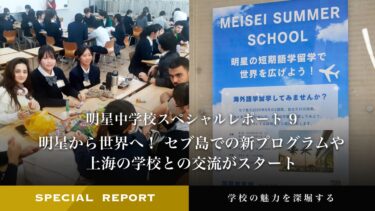聖学院と合同で、資源・環境をテーマとしたエコプロジェクトに取り組み4年。インプットだけでなく、アウトプットにも注力するように活動も進化している。
環境エコに取り組む聖学院と合同の「SDGsプロジェクト」
2021年度に聖学院と合同の「SDGsプロジェクト」を立ち上げ、初年度は「防災・共助」、2022年度からは「環境エコ」をテーマとした活動に取り組んでいる。今年度は、「菜園・コンポスト」、「資源活用」、「エネルギー」「フードロス削減」の4チームに分かれ、環境への貢献について考え、研究し、啓蒙活動を行った。「菜園・コンポスト」チームは、学内で廃棄される生ゴミからたい肥を作り、それを校内菜園の土づくりに活用。「資源活用」チームは、無添加石鹸、給水機、バガス容器*の3つの分野でプラスチックゴミの削減に取り組んだ。「エネルギー」チームは、電気使用量自体を減らす省エネと、ソーラーパネルで電気を作り、火力による発電量を減らす創エネの2つのアプローチで啓蒙活動を実施。「フードロス削減」チームは、食材を極力捨てずに美味しい料理作りを競う「クッキングバトル」を開催したり、食ベ物を必要とする人に無償で食品を提供する「フードパントリー」などに参加した。各チームは、11月の記念祭(文化祭)で活動の発表をしたり、3月の「SDGsデー」では聖学院小学校の児童に向けてワークショップなども行っている。
*バガス容器…従来では廃棄物として処理されていたさとうきびの搾りかす(バガス)を有効利用するために開発された容器
同校単体でのSDGsの取り組みでは、毎年「戦争と平和を考える」をテーマに全校生徒が感想文を作成したり、ボランティア活動としておむつや介助タオルを作り、老人ホームなどの施設に送ったりしている。
また、理科の授業では防災、家庭科で食生活、国語で薬物防止標語の作成、保健体育は障がいについての学び・パラスポーツ体験というように各教科がSDGsに関する学びを展開し、さらに近年では、中1社会科で朝日新聞社と連携したSDGsに関しての特別授業を実施したり、中3で始まった沖縄修学旅行を中心とした平和をテーマとした探究活動など、新たな取り組みを行っている。
生徒インタビュー
・聖学院高校1年Kさん
菜園・コンポストチーム コンポストのリーダー(活動1年目)
・女子聖学院高校1年Yさん
資源活用チーム バガス容器のリーダー (活動2年目)
・聖学院 高校1年Hさん
資源活用チーム 無添加石鹸のリーダー (活動3年目)
・女子聖学院高校2年Mさん
フードロス削減チーム 昨年度のリーダー (活動3年目)
「SDGsプロジェクト」に参加した理由は?
Kさん
学校でもSDGsの授業があり、その都度、“自分ができること”を書いていましたが、実際に取り組んだことはなかった。SDGsプロジェクトなら、何かしらできることがあるはずだと考え、参加しました。
Yさん
SDGsというフレーズをいろいろなところで聞いてはいたものの、行動に移す機会がありませんでした。自分一人でも何か変えられることがあったらいいなと説明会に参加し、話を聞いて興味を持ちました。
Hさん
小学生の時にSDGsや、目標が17個に分かれていることを学び、自分はどんなアクションをすればよいのか考えるようになりました。中学校に入学してプロジェクトの存在を知り、もっと大きなアクションができるのではないかと参加しました。
Mさん
中3の時に友人に誘われたのがきっかけです。これまでプロジェクト活動というものをしたことがなく、楽しそうと軽い気持ちで始めました。実際に活動してみると、環境問題は身近なことなのに知らない人が多く、もっと広めていきたいと思うようになりました。
チームでどのような活動をしたのですか?
Kさん
昼休みに回収した学食の生ゴミをハサミで切り、それをコンポストバッグに溜めて、かき混ぜたりしながらたい肥を作りました。「菜園・コンポスト」チームが掲げている目標はCO2の削減で、生ゴミの廃棄処分を少しでも減らし、焼却による温室効果ガス排出量の削減を目指しました。
Yさん
校内で使用されるお弁当のプラスチック容器の代わりに、バガス容器を仮導入したり、記念祭(文化祭)で使われるカレー容器などでもバガス容器を使ってもらいました。バガスは焼却の際に排出されるCO2が、プラスチックに比べて81%カットされます。また、記念祭(文化祭)では、使用した容器を土へ返す取り組みもしました。
Hさん
昨年度はオリジナルの無添加石鹸を作るといった体験型ワークショップを開き、今年度はすごろくゲームを作って、環境問題を発信しました。また、今年度から自由研究フェスタやサイエンスアゴラなど、外部のイベントにも参加しました。サイエンスアゴラでは環境省の方とつながることができ、後日、話を聞く機会を持ちました。
Mさん
昨年度は荒川区のフードパントリーで食品配布のお手伝いをし、今年度はその経験をもとに、記念祭(文化祭)で外部の方や生徒の保護者から食品を集めて、王子の子ども食堂に届けました。食品を集めて届けるところまで、自分たちの手で行うという目標を達成することができました。また、この3月の「SDGsデー」では、聖学院の小学生に向けてフードロスを学んでもらう授業を行う予定です。
プロジェクト活動のやりがいや、活動を通じて成長したと思うことはありますか?
Kさん
自分たちの活動が形として見えた時にやりがいを感じます。一時期、コンポストバッグ内の微生物の活動が悪くなり、温度を測ってデータを蓄積したら、25度が最適であることがわかりました。このように仲間と協力して問題を解決する力や、また責任者として状況を整理し、物事を進める力が身についたと思います。
Yさん
昨年は先輩の指示に従って動いていましたが、今年度は自分がリーダーとして、チームの意見を聞いてまとめたり、先生と連絡を取り合うなど、積極的に動く姿勢が身につきました。また、活動の成果を発表する機会が年に3回あり、プレゼンの力も向上したと思います。
Hさん
1回、1回のワークショップは、年齢層など対象者が異なり、相手に合わせて伝えるという適応力がつきました。また、リーダーとしてみんなを率いたり、意見を調整する力も備わったと思います。すごろくを作る時もチームで意見が分かれたら、「何を一番学んでもらいたいのか、原点に戻ろう」と、一歩引いて声をかけたりしました。
Mさん
記念祭(文化祭)の時にたくさんの人から食品を寄付してもらったり、SDGsのブースでポスターを目にしてもらえた時にやりがいを感じました。また。子ども食堂で子どもたちが喜んでくれた時もうれしかったです。また、プロジェクトに入るまで人前で発表する経験がなく苦手だと思っていたのですが、やってみたら楽しかった。それが自信になり、高1では運動会の主将に自分から立候補しました。
活動を通じて、SDGsに対する考え方が変わりましたか?
Kさん
来年度は、回転式コンポストかミミズコンポストを取り入れて、より効率良く、かつ省力化してたい肥作りをしたいと考えています。
Yさん
バガス容器が本導入までいけていないので、導入したいと考えています。また、学校内では不燃と可燃ゴミの分別がきちんとできていないことが多く、来年度は整備委員長も兼務するため、ゴミの分別とバガス容器の両方で、啓蒙活動を行っていきたいです。
Hさん
ワークショップやゲームをもっとブラッシュアップして、それを有料化し、環境問題の活動している団体に寄付するなど、社会に関わっていけたらいいなと思っています。
Mさん
私は今年度で引退しますが、来年度はもっと学校外へ活動の場を広げることを期待しています。聖学院小学校で給食の食べ残しを調べたところ、結構な量があり、それはどこの小学校も同じだと思うので、地域の小学校などでもフードロスの授業やワークショップができればよいと思っています。
同校のその他の取り組み
聖学院と合同で、資源・環境をテーマとしたエコプロジェクトに取り組む。ボランティア活動や教科の授業でもSDGsの取り組みを実践。
環境エコに取り組む聖学院と合同の「SDGsプロジェクト」
2021年度に聖学院と合同の「SDGsプロジェクト[…]
女子聖学院中学校
【所在地・交通アクセス】
〒114-8574 東京都北区中里3-12-2
TEL 03-3917-2277
- JR「駒込駅」より徒歩7分
- JR「上中里駅」より徒歩10分
- 南北線「駒込駅」より徒歩8分
MAP



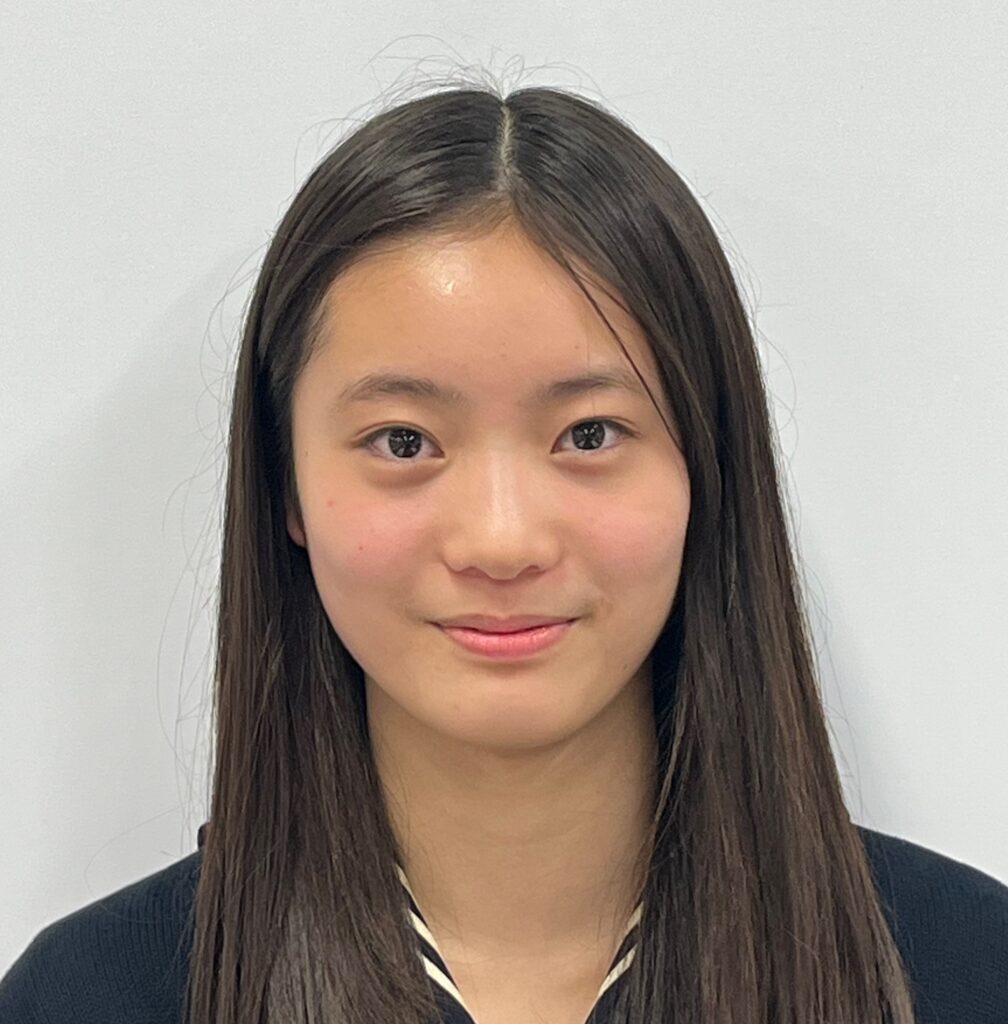



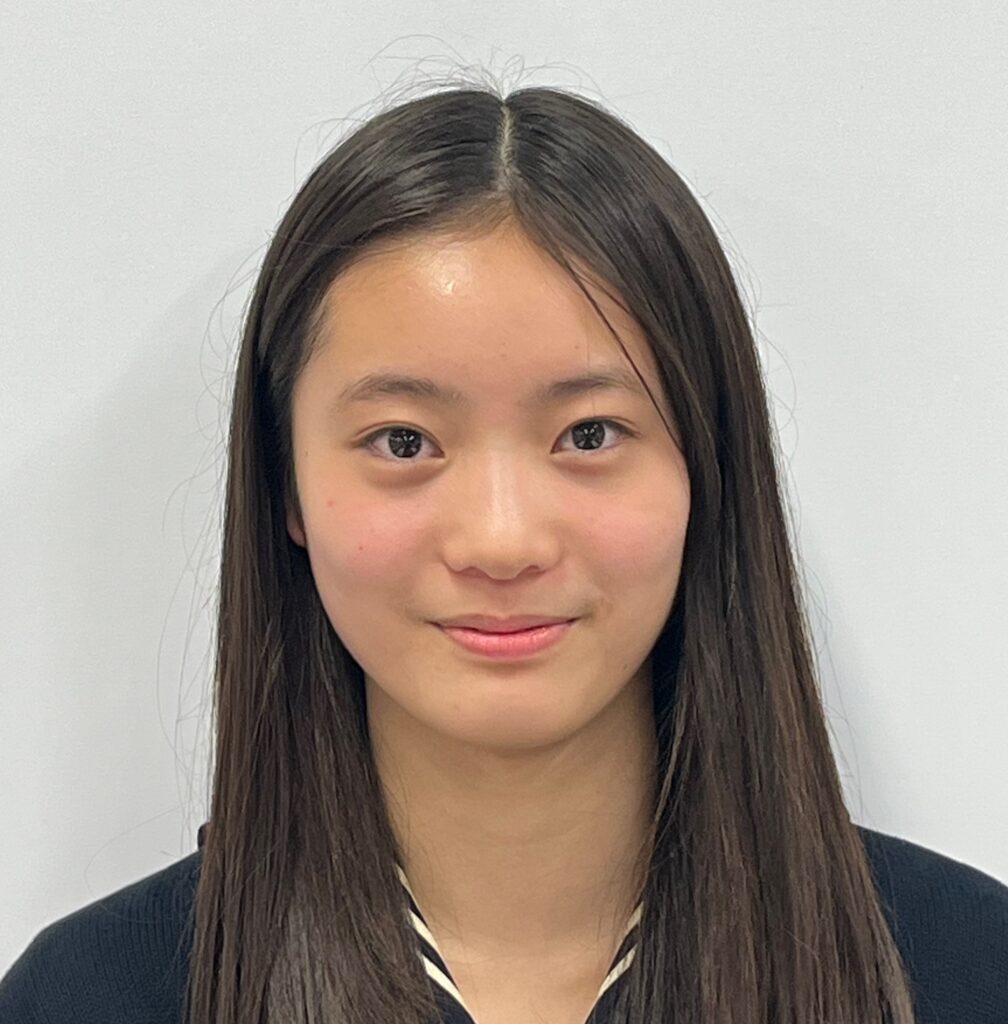



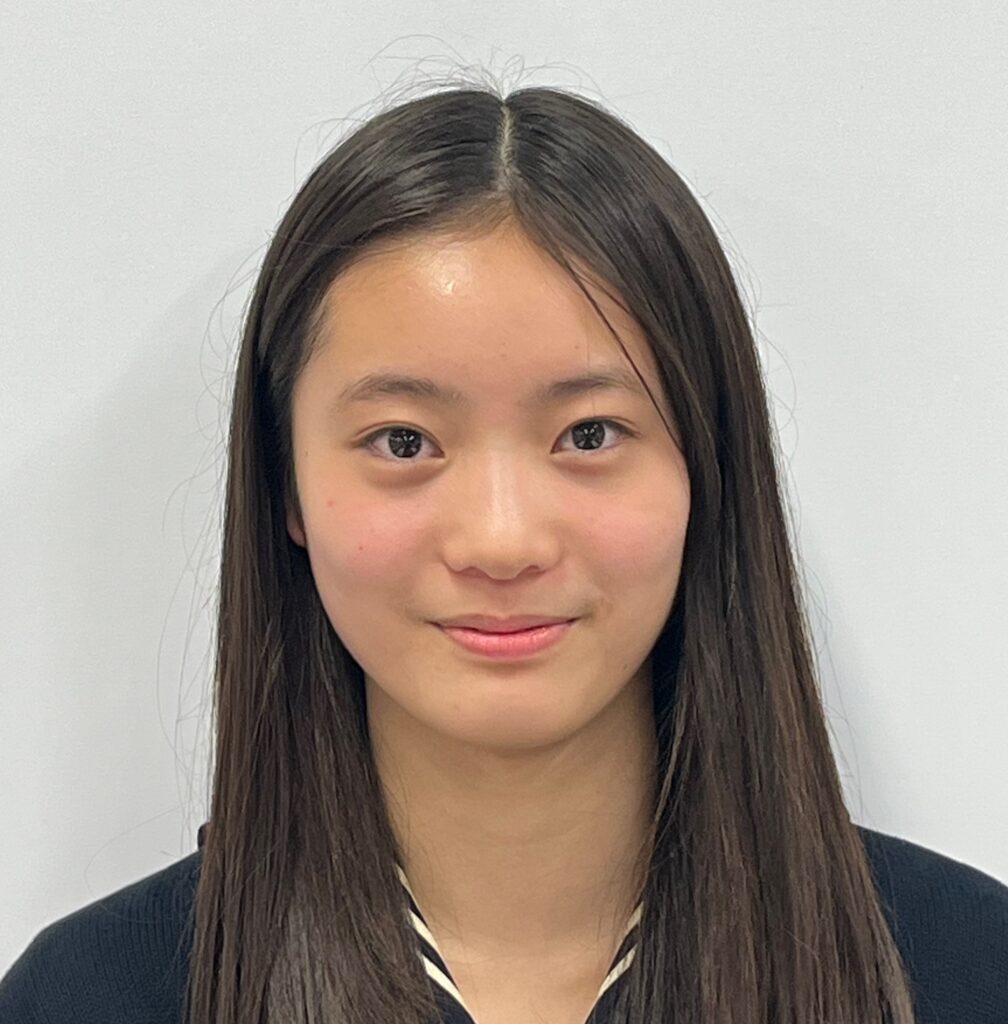



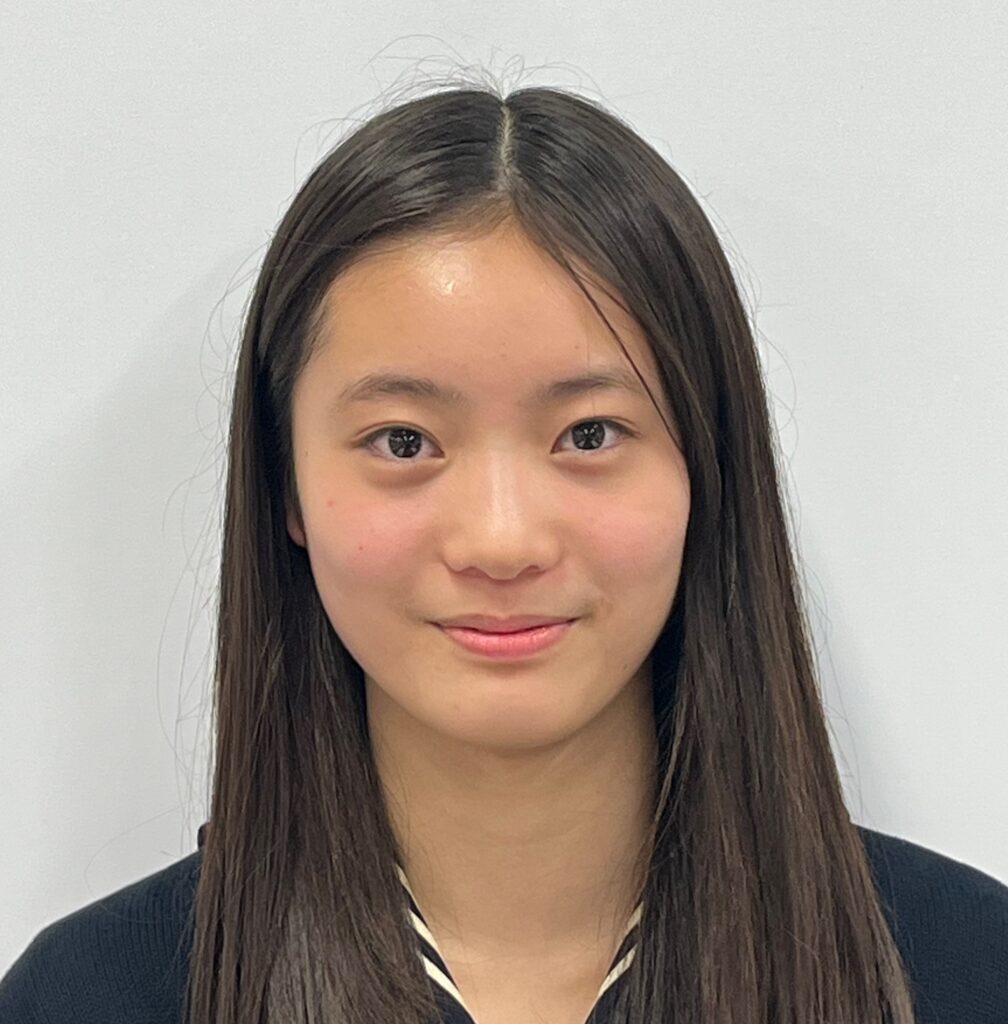









![[SDGs特集]聖学院中学校/環境エコに取り組む女子聖学院と合同の「SDGsプロジェクト」](https://studypass.jp/wp-content/uploads/2025/03/seigakuin7-scaled-1-375x253.jpg)