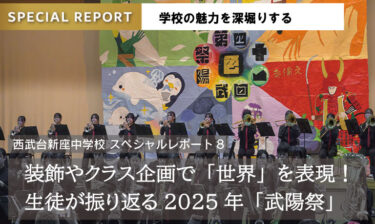Special Report
日本有数の総合大学である関西大学には「関西大学第一中学校」「関西大学北陽中学校」「関西大学中等部」の3つの併設校がある。それぞれの教育方針や学びの特色には違いがあり、進学先としての魅力も多彩である。本記事では、三校の入試広報主任教員にインタビューを実施。保護者が学校選びをする際のヒントとなる情報をお届けする。
Index
中学から大学の学びに触れる
各併設中学校では、中学生が大学の学びに早くから触れられる機会がある。
学校によっては、現役大学生がキャンパスを案内するものや、学部の特色を活かしたプログラムなど、多彩な内容が揃う。
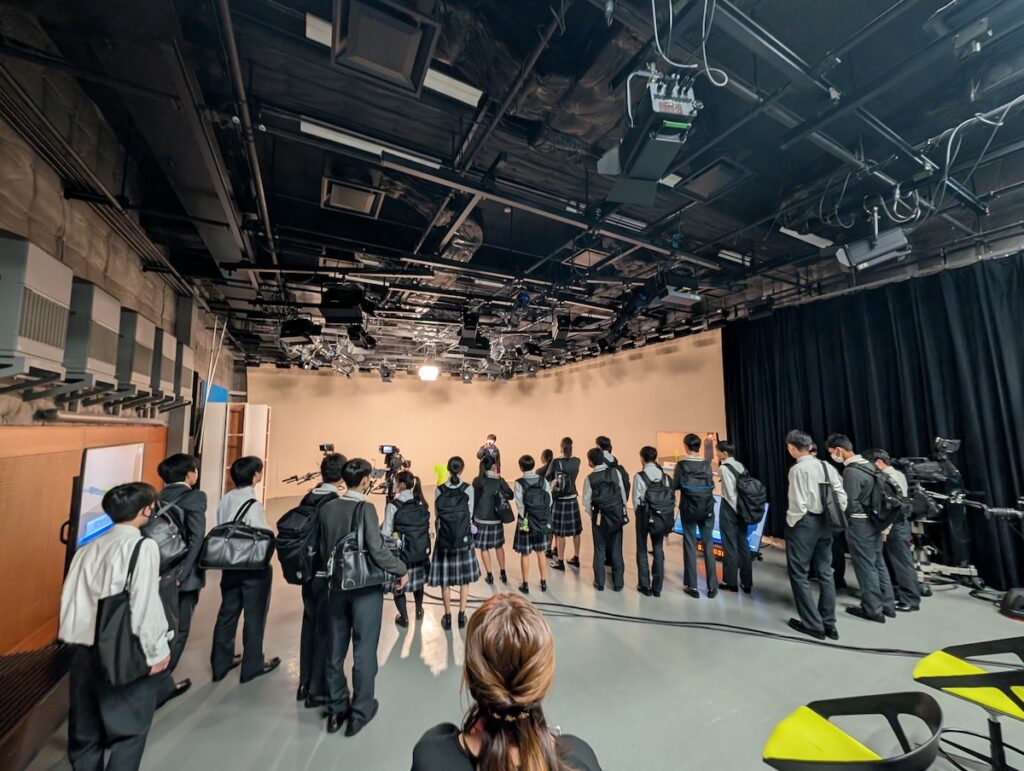
高校においては、主に「関西大学併設校連携プログラム」を展開。
生徒が学部の学びや魅力をより深く理解し、自らの興味や将来を意識したうえで学部選択ができる。プログラムによっては中学生から参加することも可能だ。
関西大学への内部進学制度があるだけでなく、大学入学後につながる取り組みを多数展開する関西大学併設校の“今”についてレポートする。
関西大学第一中学校
関西大学第一中学校・高等学校では、「丘陵の学び舎」をコンセプトに校舎の大規模改築を進めている。2023年末には、プレゼンテーションエリアや図書室、中学2・3年の教室を備えた新校舎「景風館」が完成。2026年4月には、高校の新校舎も竣工予定だ。
「本校は授業後の時間を大切にする、いわば『昔ながら』の学校。やりたいことに打ち込んでいる生徒たちは本当に楽しそうです」と語る入試広報主任・狩場治秀教諭に話を聞いた。

「やりたいこと」に本気で取り組める、昔ながらの学校
「本校の一番の強みは、生徒です」。そう語るのは、同校で入試広報主任を務める狩場教諭だ。
「生徒たちは、日々楽しそうに授業を受け、部活動をはじめとするさまざまな活動に意欲的に取り組んでいます。その姿を説明会などで見て、本校を志望されるご家庭が本当に増えました」
同校では、オープンキャンパスの企画・運営を生徒会に任せており、中1・2だけで100名以上の生徒がお手伝いに手を挙げるという。
「オープンキャンパスでは、在校生が訪れた保護者と受験生を連れて校内を案内します。参加した保護者から『なぜ、生徒たちはこんなに楽しそうなのですか?』と聞かれることも少なくありません」
狩場教諭は、その理由の一つに、入試が1回のみで、入学生のほとんどを第一志望の生徒が占める点を挙げる。
「『ここで学びたい』という強い思いを持つ生徒が集まっているため、学校全体の雰囲気も自然と明るく前向きになります。校則は決して緩くはありませんが、厳しく指導しなくても、生徒たちはきちんとルールを守ってくれています」
保護者からも似た価値観を持つ生徒が多く、「安心して友達付き合いを見守れる」といった声が寄せられているそうだ。

そして、やりたいことに打ち込める環境が整っているから、生徒がいきいきと過ごせる、と狩場教諭は続ける。
「やりたいことに本気で打ち込んでほしいと、授業はどの曜日も6限目までにしています。また、関西大学への内部進学には日々の学習にきちんと取り組んでいれば大丈夫。塾に通う必要がないので、高校生でも部活の入部率は94%です。他にも、習い事を続けたり、宝塚音楽学校やプロ棋士を目指したりする生徒もいます」
関西大学第一高校への内部進学が基本ではあるが、毎年10人ほどは外部高校へ進学する生徒もいる。
「6クラスあるので、1クラスに1人ほど。中にはスポーツや芸術の道、公立トップ高校への進学を目指す子もいます。それは本人の意思を尊重して、応援しています」と狩場教諭は話す。
併設校でありながら、一人ひとりの“やりたい”を大切にする姿勢が、生徒たちの「学校が楽しい!」という想いにつながっている。
2023年末に図書室を備えた新校舎が竣工

同校では、2023年末に新校舎「景風館」が完成した。
中学2・3年生の教室や中高共用の図書室などが設けられ、生徒の学びを多角的に支える。
窓を大きく取られた新教室は、明るく開放感のある雰囲気。大きなホワイトボードが設置され、ICT機器を効果的に活用した授業が展開される。
図書室には4万6千冊を超える蔵書がそろう。ジャンルは実に多彩で、話題の新刊が表紙を見せる形で陳列されている。読む意欲をかき立てるポップが至る所に添えられ、長期休暇前にはテーマに基づいた“本の福袋”も登場。生徒の手が本に伸びる工夫が随所に施されている。
階段状のプレゼンテーションエリアや、グループでの探究活動に適したコモンズエリアも新たに整備。
プレゼンテーションエリアは放課後には自習室としても利用でき、図書室で借りた本を手に学習に励む生徒の姿も多い。
「新校舎の完成を機に、新しい教育にも挑戦していこうと、2024年度には台湾にある中学校とオンライン交流会も行いました。コモンズエリアには大型モニターを備えた教室も2つあり、そういった交流にも活用できますので、積極的に活用していきたいですね。2025年度は、イタリアやカンボジアの学校との交流を企画中なんですよ」と狩場教諭は展望を語る。
新校舎をきっかけに、学びの舞台を広げる同校。
意欲的に学校生活を楽しむ生徒たちが、新しい教育を未来へどうつなげていくのか、期待が高まる。
関西大学北陽中学校
関西大学北陽中学校・高等学校は、目標に応じたコース制を高校1年次から導入している唯一の併設校だ。
高校には「特進アドバンス」「文理」「進学アスリート」の3コースがあり、中高一貫生は、難関国公立大学への進学も視野に入れた「特進アドバンス」か、関西大学への進学に特化した「文理」かを選ぶことができる。
どちらのコースにも対応できるよう、中学校では日々の宿題や小テストを通じて、基礎から応用まで着実に学力を身につけていく指導体制を整える。
「学力面での丁寧なサポートに加え、豊富な学校行事や充実した部活動が揃っているバランスの良さが本校の魅力です」と語る広報部主任の松風啓教諭に話を聞いた。

こまやかな目標設定で、学びに前向きな姿勢を育む
2023年度入試から、同校では複数回受験による加点制度を導入した。
その結果、第一志望で入学する生徒が増加し、入学後の生徒たちの学びにも好影響を与えているという。
「『この学校でがんばりたい』という思いを持った生徒が入ってきてくれるようになったことで、学習に対する意欲が高まり、学力の伸びにもつながっていると感じています」と松風教諭は語る。
授業の様子のコピー-1024x683.jpg)
同校では、こうした意欲ある生徒たちを支えるきめ細やかなサポート体制を整えている。たとえば、定期テスト前には担任との個別面談を実施し、勉強の進捗状況を確認。
さらに、全学年の生徒にスケジュール帳と「振り返りノート」を持たせ、日々の学びを記録させている。
「振り返りノートはその日の学びを自分なりに振り返る日記のようなものです。担任と生徒のコミュニケーションのきっかけにもなります」
同校では、授業は月曜日のみ7限、それ以外は6限で終了する。
放課後は多くの生徒がクラブ活動に向かうが、学習に遅れが見られる生徒や、小テストに合格できなかった生徒、宿題未提出の生徒などには、7限を活用して補習を行う。
「私たちは、希望する生徒全員を関西大学へ送り出すために、学習面で取り残される生徒を出さないことを最も大切にしています。そのためにも、学習面で取り残される生徒を出さないことが何より重要だと考えています」と松風教諭。小テストも頻繁に実施し、中学校の学習内容は中学校のうちにきちんと定着させることを重視しているという。
「宿題や小テストがあるほうが頑張れるタイプのお子さんには、うちの学校はとても合っていると思います」と松風教諭は笑顔を見せる。12歳の時点で、自律的に勉強できる生徒はそう多くはないだろう。
そんな生徒たちに教員がしっかりと寄り添い、継続して力を伸ばしていける環境が、同校の魅力の一つだ。
学びのすそ野を広げて、高い学力と人間力を養う
同校では、高校で企業と連携した大規模な探究プロジェクトを設定しており、それにつながるよう、中学校でも系統立てた探究の学びを「総合学習」の時間で行っている。
1年生では「ブックプロジェクト」「ビブリオバトル」を実施。
自分の言葉で本の魅力を伝えることに挑戦し、相手にどう伝えれば興味を持ってもらえるかを考えることで、表現力を磨く。
ビブリオバトルのコピー-1024x768.jpg)
2年生になると、新聞記事を教材とするNIE(Newspaper In Education)を導入。
興味を持った記事を選んで要約し、自分の言葉で説明するなどの活動に取り組む。
松風教諭は「その中で『もっと深く調べないと説明しきれない』といった気づきが生まれ、自ら学びを深めようとする姿勢も育まれていきます」と説明する。
そして3年生では、SDGsの17の目標をテーマに、「私たちにできること」を考えるグループワークを実施。
生徒たちは自らの興味や疑問を出発点に、アンケート調査や外部企業への取材など、本格的な探究活動に踏み出していく。
「こうした取り組みを通じて、生徒たちは与えられた課題をこなすだけでなく、自ら問いを立て、深く探究し、社会に向けて発信できる力を育んでいきます。中学で3年間探究の経験を積んだ一貫生は、高校での探究活動ではリーダーとして活躍してくれます」
ただ、「これらの取り組みについて、短期的な目標は設けていません」と松風教諭は続ける。
「ほかにも、本校では中大連携プログラムや希望制の海外研修、多彩な学校行事など、学びの機会を豊富に用意しています。しかし、これらの取り組みについて、“これをやったからこういう成果がある”といった考えではなく、ただ、生徒の興味や関心の幅を広げる一助になればという想いで取り組んでいます。人としてのすそ野が広がれば、それが自然と高い学力と人間力につながっていくと考えるからです」
ただ座学で知識を積み上げるのではなく、幅広い学びを展開し、人を育てていく。目の前の受験に追われない併設校ならではのゆとりは大きい。
関西大学中等部
関西大学中等部は、全学年あわせて中等部は3クラス、高等部でも4クラスという小規模編成をとっているのが、他の併設校との大きな違いだ。
同校では小規模校ならではのきめ細やかな教育のもと、自ら考え、主体的に行動して責任をもってよりよい社会を築くための力「考動力」を持った人材の育成をめざす。同校の教育について、入試広報部主任の多久島亮教諭に話を聞いた。

少人数だからこそ生まれる、あたたかい人間関係

同校は併設校の中で唯一、初等部を設置しており、中等部では内部進学の生徒と中学から入学した生徒が共に学ぶ。
「初等部からの内部進学者がいる中で、中学から入ってきたお子さんがすぐに馴染めるかどうかを気にされる保護者の方もいらっしゃいます。しかし、本校は1学年の人数が少ない分、生徒同士の距離が近く、自然と関係が深まっていきます。中学から入学した生徒も、無理なく学校生活に溶け込んでいますよ」と多久島教諭は語る。
4月の入学式の翌週には琵琶湖での宿泊研修を、5月には体育祭を実施するなど、入学直後から仲間と打ち解ける機会を豊富に用意。
体育祭では、クラスごとに赤・青・黄の3団に分かれて競い合うため、クラスの一体感が高まるという。
校舎の構造も、あたたかな人間関係の形成に一役買っている。
多久島教諭は「全クラスが1フロアに集まっているので、自分の学年全員の顔と名前が自然とわかるようになります。教員の目も行き届きやすく、生徒にとっても安心できる環境です」と説明する。
また、入試関連イベントにおいても、学年を越えたつながりが生まれる。
「オープンスクールや学校説明会、入試説明会では、生徒たちが運営を担当します。中学1年生から高校2年生まで、今年は約60名が立候補してくれました。学年混合のチームで活動する中で、先輩・後輩とも仲良くなれます」
こうした日常の積み重ねが、学校全体にアットホームな空気を育んでいる。まるでひとつの家族のような温かさこそが、同校の魅力だ。
国際理解教育×探究活動で「考動力」を育む
同校では創設当初から「探究活動」と「国際理解教育」を教育の両輪と位置づけ、この2つを連動させながら、系統的な学びを展開している。
まず1年生では、地元・高槻市を知ることからスタート。フィールドワークを通じて高槻という街を深く学んだ後、「都市交流・地歴・自然・福祉」の4系統に分かれて、「高槻を知り、高槻に関わり、高槻の人とつながる」プロジェクトに取り組む。生徒たちは今の高槻の姿を踏まえつつ、高槻の未来を自分たちの視点で考える。
2年生のテーマは「産業という観点から地域を知る」。前半は産業について学び、11月には和歌山県・日置川への宿泊研修を実施。さらに2月の総合学習発表会では、日置川の魅力を発信する「物産展」を開催する。
「日置川での研修では、現地のご家庭に民泊しながら、地域の産業構造や抱える課題について、自らの目で確かめることができます。そのうえで、異なる産業同士を結びつけることで、どのような価値が新たに生まれるのか、また、地域の未来をどのように守っていけるのかを、自分なりに考察してもらいます」
3年生では、「高槻、地域、世界の人とつながり、自分のあり方を考える」ことがテーマ。これまでの学びを踏まえ、自分自身のアイデンティティについて考えたうえで、カナダ研修旅行へと向かう。
ホームステイや現地校との交流を通じて、異文化理解を深め、自分自身を見つめ直す。

「多民族国家であるカナダの家庭に滞在することで、日本の文化や自分自身の特長について考えるきっかけになります。最初は戸惑う生徒も多いですが、学年全員で取り組むからこそ、安心感があり、帰国後には『ずっと向こうにいたかった』というほど、心に残る体験になります」
2年生の民泊も、3年生のホームステイも、学年全員で実施できるのは小規模校ならではの強みだ。
理科の実体験を通して育む「考動力」
同校では理科教育にも力を入れており、日常的に体験的な学びができる環境を整えている。
物理・化学・生物・地学の各分野に対応した専用実験室が4教室あり、それぞれの教室には専門的な設備が充実。
さらに、複数の実験助手が常駐し、授業の準備や安全管理など、細やかなサポート体制も整っている。

「顕微鏡などの器具は、生徒一人ひとりに行き渡るように準備しています。実験だけでなく、校舎の目の前にある公園に観察に行くこともあります。これらの学びが実現できるのも少人数だからです」と多久島教諭。
こうした実体験重視の理科教育は、高等部に進学してからも継続。
高1はもちろん、高2・高3においても実験の機会を可能な限り確保しており、「実験の多さに驚いた」と話す高校入学生も多いという。
「実験では思いがけないことが起こることもあります。そうした中で、自ら考え、仲間と協力しながら答えを導く過程こそが、“考動力”を育てるのです」
単なる知識の習得にとどまらず、「考動力の育成」という教育理念のもと、生徒一人ひとりの成長へとつながる教育が、ここにはある。
取材を終えて
取材に伺ったのは7月中旬。すでに猛暑と呼ばれる時期であったが、どこの学校でも楽しそうに部活動に打ち込む生徒の姿がたくさん見られた。公立中学校では、部活動の地域移行が進められつつある。また、私立中学校であっても、活動日数を制限している学校も少なくないと聞く。そういった時代において、自分のやりたいことを見つけ、それに打ち込める環境で6年間過ごせることの意義は大きいと感じた。
関西大学第一中学校<所在地・交通アクセス>
〒564-0073
大阪府吹田市山手町3-3-24
TEL 06-6337-7750
- 阪急千里線「関大前駅」より徒歩3分
関西大学北陽中学校<所在地・交通アクセス>
〒533-0006
大阪府大阪市東淀川区上新庄1-3-26
TEL 06-6328-5964
- 阪急電鉄京都本線「上新庄駅」南出口より徒歩8分
- 阪急電鉄千里線「下新庄駅」より徒歩10分
関西大学中等部<所在地・交通アクセス>
〒569-1098
大阪府高槻市白梅町7番1号
TEL 072-684-4326
- 京都線「高槻駅」より徒歩7分
- 阪急京都線「高槻市駅」より徒歩10分